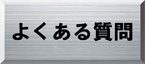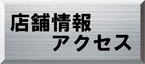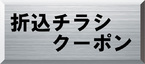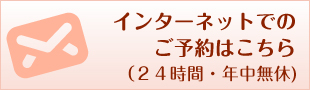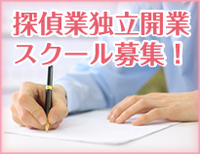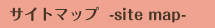森田療法を考案した森田正馬は1874年に生まれ、1938年に肺炎で死去。1898年、東京帝国大学医科大学入学。1903年、東京慈恵会医院医学専門学校教授となる。森田療法の確立は1920年頃といわれています。
森田療法は、対人恐怖や広場恐怖などの恐怖症、強迫神経症、不安神経症(パニック障害、全般性不安障害)、心気症などが主たる治療の対象であり、これまでに高い治療効果をあげてきています。
また最近では、慢性化するうつ病やガン患者のメンタルケアなど、幅広い分野に有効と言われています。
森田療法では、症状への、
「あるがまま」の心の姿勢を獲得できるよう援助します。
「あるがまま」とは、第一に不安や症状を排除しようとすることをやめ、
そのままにしておく態度を養うことです。第二には、不安の裏にある生の欲望(向上発展の希求)を建設的な行動に発揮していくことです。
森田療法とは、不安を抱えながらも生活の中で必要なこと
(なすべきこと)から行動し、建設的に生きることを教え、実践させる治療方法です。
つまり、
「あるがまま」という心の改善によって神経症(不安障害)をのりこえていくことです。
【森田療法の考え方】
森田療法の治療に対する基本的な観点は、次のような人間理解を前提にしています。神経症の根底に共通する心理は、死の恐怖や不安だということです。
人間の生涯は限られており、誰もが必ず死に直面します。
ですから、死を恐怖する感情は、本来人間にとって免れることのできない普遍的なものです。
同時に死の恐怖の裏には、より良く生きようとする「生の欲望」があります。
不安や死の恐怖を抱く心の底には生の欲望、つまりよりよく生きよう、向上発展しようとする欲望があるということで、それらは表裏一体のものだと理解することが、森田療法のひとつの特徴です。
神経症の人は、自然な心の一部である死の恐怖を一生懸命に排除しようとし、内的に葛藤を起こしているのです。森田療法では死の恐怖や不安はそのまま認めます。
認めたうえで、精神交互作用と思想の矛盾から脱出し、自然に従った心のあり方に沿って生の欲望をもっと発揮していこうとするものです。
 【森田療法の治療方法】
【森田療法の治療方法】
「あるがまま」という言葉に象徴されるように、それまでの不安に対する態度を転換させることです。
神経症の人は、不安と必死に戦ってそれを排除しようとし、ますます不安を増長させています。
その戦いをやめ、不安をそのままにしておく態度を醸成していくのです。
「あるがまま」というと、症状を我慢しろ、もしくはあきらめろといったニュアンスで受け止められることがありますが、森田療法での「あるがまま」は単なるあきらめとは異なり、
もう少し積極的な意味合いがあります。不安の裏にある生の欲望を、もっと建設的な行動に発揮していくのです。このことが治療の基本的な考え方の二つ目です。
言い換えれば、症状をあるがままに認めたうえで、自分を生かしていくということです。
そういう意味で、単に症状が起こらないようにすればいいというのではなく、その人の心の成長を促すことも、治療の最終的な目標になります。
森田療法において大事なのは、不安の裏には自分が向上・発展したいという強い欲望が存在しているからこそ悩んでいる
(=不安と欲望は表裏一体)ということを、
本人が体験によって実感することです。
そのため、不安や恐怖を排除しようとせず、あるがままにおきながら自分の建設的な欲求にしたがって活動していくことを、
体験的に身につけるのです。これらのことは、頭で理解するだけでは不十分なのでカウンセリングが大切になります。
メンタルケアサロン心の翼 千葉八街本店の入院療法しない 心の翼 森田療法カウンセリングお勧めいたします。
メンタルケアサロン心の翼 千葉八街本店の心理カウンセラーと一緒に心のケアをしてみませんか?